「出産に関する助成金って何がもらえるの?」「実際どのくらい戻ってくるの?」と不安になりますよね。
結論、制度を上手く利用すれば3年間で600万円以上貰うことも可能です!
そこで今回は、出産前後でもらえるお金や支援制度を2025年最新版でまとめてご紹介します。
体験談も交えて、リアルな金額・注意点・申請のコツなどもお伝えします!
※この記事は、2025年4月時点の情報です。今後制度の変更がある可能性もあります。
出産でもらえるお金一覧
| 出産前/後 | 申請時期 | 名称 | 支給額 (目安) | 計算方法 | 申請先 | 受給時期 | 条件・事例 |
| 出産前後 | 産後56日以降 | 出産手当金 | 約50万〜70万円 | (標準報酬月額 ÷ 30)× 2/3 × 日数(98日など) | 健康保険(会社経由) | 約1〜2ヶ月後 | 健保加入+休業/月収30万で約65万円支給 |
| 出産後 | 出産後すぐ | 出産育児一時金 | 子1人につき50万円 | 定額 | 健康保険(病院が代理請求も可) | 医療機関により即時または後日 | 双子=100万円/帝王切開も対象 |
| 出産後 | 出産後すぐ〜育休開始時 | 育児休業給付金 | 月収の約67%→50% | 賃金日額×支給日数×割合 | ハローワーク(会社経由の場合も) | 約2ヶ月ごと | 雇用保険+1年勤務/月収30万→20万支給例 |
| 出産後 | 出生届提出後すぐ | 児童手当 | 月1万〜1.5万円/子 | 定額 | 市区町村役所 | 原則、翌月から支給 | 3歳未満は月1.5万円/中学卒業まで支給 |
| 出産後 | 妊娠届提出時 | 妊婦健診助成 | 約10〜14回分(数万円) | 実費補助(受診券など) | 市区町村役所 | 健診時に都度適用 | 東京では最大10万円相当/直接支払不要 |
| 出産後 | 出生届と同時 | 乳幼児医療費助成 | 自己負担0円〜数百円 | 子どもの医療費実費を軽減 | 市区町村役所 | 医療費支払い時から | 通院200円上限など自治体による/所得制限あり |
| 出産後 | 出生届・住民票手続き後 | 出産祝い金(自治体) | 数千円〜10万円以上 | 定額(自治体差) | 市区町村役所 | 数週間〜数ヶ月後 | 奈良県王寺町:第2子で10万円支給 |
| 出産後 | 出生届+ひとり親申請後 | 母子家庭・父子家庭手当 | 月額数千円〜4万円超 | 所得・子の人数で算出 | 市区町村役所 | 翌月以降に毎月支給 | 月5万円支給例/所得制限あり |
| 出産後 | 翌年2月〜3月(確定申告) | 医療費控除 | 税還付(数千〜数万円) | 医療費-10万円)×所得税率 | 税務署またはe-Tax | 還付は数週間〜数ヶ月後 | 帝王切開+健診費→控除対象になる |
| 出産後(3歳〜) | 保育利用申請時 | 保育料無償化 | 月3〜5万円相当 | 実費免除 | 市区町村役所 | 月ごとに減額・無償 | 認可園で3歳〜5歳原則無料/所得条件あり |
実際にもらえる金額は?
マネー調査員の実例 第一子 子供が3歳になるまでに約682万円
出産手当金 906,880円
※3月頭に出産し3月末に手続き、5月25日に振り込み
出産育児一時金 420,000円(産科医療補償制度に加入済の医療機関で出産した場合)
※マネー調査員は健康保険から病院側に振り込んでもらって、足りなかった分を病院に支払うパターンにしました。
※令和5年4月以降は制度が改定されて、支給額が50万円に引き上げられました。
育児休業給付金 2年間4,752,036円
出産から6ヶ月までは、賃金月額の67%244,536円(2ヶ月毎に489,072円の振り込み)
産後6ヶ月から子供が2歳の誕生日を迎えるまで、賃金月額の50%182,490円(2ヶ月毎に364,980円の振り込み)
※元々、賃金月額 364,980円(手取りは27万円ぐらいでした)
※初回振り込みがひたすら時間がかかります。半年は覚悟しておいてください。
※マネー調査員は、保育園激戦区で落ち続けたので2歳までもらい続けることとなりました。
児童手当 0歳〜3歳未満 毎月15,000円(3年間で540,000円)
※2025年現在所得制限がありますが、2025年10月以降で廃止に向けて動いているそうです。
※夫婦のうち所得が高いほう1人分年収が、約961万円以上の場合月5,000円
※自分の口座に振り込まれるようにしたほうが何かといいいですよという老婆心です。
妊婦健診助成
市役所に母子手帳を貰いに行くと、妊婦健康診査費用を補助するための14枚の補助券をもらいました。
例えば東京都では妊婦健診1回目:11,280円、妊婦健診2回目以降:5,280円などとなっています。
補助券の金額はいくつかあるので、最初はどう使っていいのか分からなかったのですが、
病院での会計時に、係の方が適切な補助券を使ってくれるので、何も考えずに差額分だけ出していました。
感覚ですが、妊娠中の通院費に関しては6割~8割の費用はこの補助券で賄えるのですが、それでも毎回2,000円~4,000円は何かしら支払ってました。
乳幼児医療費助成
自治体によります。
マネー調査員の自治体では小児医療証というカードがもらえました。
子供が病院を受診する際には、窓口に保険証(またはマイナカード)とこの小児医療証を出すと、自己負担分を助成してくれます。
マネー調査員の自治体では当時子どもの医療費がどんなに掛かっても上限500円の負担で済みました。
出産祝い金(自治体)
マネー調査員の住んでいた自治体では、当時現金などではなく「産前・産後ヘルパー派遣」の補助券みたいなものがありました。
しかし無料になるわけではなく、通常1時間2,000円ぐらいかかるのが、500円になりますみたいなものでした。
しかも市がリストアップした派遣元の企業の中から、受け入れてくれそうな企業を選んで自分で電話して、
派遣してもらえるのか、スケジュールはどうかの確認をしたのち、再度市役所で補助券が使える手続きをおこなうという果てしないものでした。
産後に赤ちゃんを抱えての手続きは諦めました。
母子家庭・父子家庭手当
驚くほどたくさんの支援があります。絶対に活用すべきです。
各市町村の役場で相談するのもいいですし、WEBサイトを見れば「ひとり親のしおり」のような案内があり、そこである程度情報が網羅されていますので絶対に使ってください。
例えば、東京、神奈川、千葉、埼玉だけでもこれだけの情報があります。
【東京】シングルママ・シングルパパ くらし応援ナビTokyo
【神奈川県】ひとり親家庭支援制度のご案内
【千葉県】ひとり親家庭への支援
【埼玉県】ひとり親家庭
医療費控除 約20万円
1年間(1月〜12月)で合計10万円以上の医療費を支払ったら、確定申告をすれば一部が所得控除されて、税金が戻ってくる制度です。
控除される額 「支払った医療費 - 保険金などの補てん額 - 10万円」
夫が確定申告をしていましたので、不妊治療のための費用も含めて約20万円ほど戻ってきました。
出産で医療費控除の対象になる費用(例)
- 妊婦健診(助成外分)
- 分娩費・入院費
- 帝王切開費用
- 通院のための交通費(電車・バス)
- 不妊治療の費用
- 医師が必要と認めた薬・処方薬
- 小児科・歯科・皮膚科などの診療費
- 子どもの入院費や治療費
※ベビー用品代、予防接種、民間保険料は対象外 なので注意!
保育料無償化
マネー調査員の家では第一子が2歳でようやく保育園に滑り込めたのですが、
2歳では収入に応じて毎月費用がかかります。上限は7万円程度です。
・3〜5歳児のすべての子ども 幼稚園・保育園・認定こども園などの利用料が無償(全国共通)
・0〜2歳児の子ども 住民税非課税世帯のみが対象 → 無償化の対象になる
マネー調査員の実例 第二子 子供が3歳になるまでに約703万円
出産手当金 847,509円
出産育児一時金 50,000円
※令和5年4月より、42万円から50万円に引き上げられました。
※妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、支給額が48.8万円
育児休業給付金 2年間3,341,190円
賃金月額256,620円
出産から6ヶ月までは、賃金月額の67%171,935円
産後6ヶ月から子供が2歳の誕生日を迎えるまで、賃金月額の50%128,310円
傷病手当金 約18万円
妊娠中働けなくなっても、手当がもらえる場合があります。
仕事を4日以上休んでいると、健康保険協会から傷病手当金を貰えます。
会社から支払われるわけではなく、健康保険から出ます。
会社経由で手続きするのか、協会に直接手続きするのか、一度会社にご相談ください。
マネー調査員は第二子出産時に、切迫流産&早産&その他色々と重なりまして3ヶ月入院しました。
有給は1ヶ月で使い切り、産休に入るまでの残り1ヶ月ちょっとぐらいは傷病手当金約18万円を頂きました。
高額療養費制度 約18万円
第二子は色々とトラブルがあり、医療費の支払いが約110万円ぐらいになりました。3割負担でこれです。入院が長かったので、医療費適応外の食費やベッド差額分や自費治療費なども重なりました。
当初は、まさかこんなに状態が悪化するとも思っておらず、病院窓口に高額療養費制度の適応の相談もしていません。
例えば、マネー調査員はざっくり6月13万円、7月15万円、8月42万円、9月40万円の医療費がかかりました。恐ろしいことにこれは出産一時金50万円を支払った後の金額です。
高額療養費を適用すれば数万円になるだろうと思いましたが、人生そう上手くはいきません。
6月7月に関しては、保険適用の医療費で限度額を超えておらず、高額療養費の適用外でした。
8月9月は適用されましたが、合計で返ってきたのは約18万円です。
ちなみに高額療養費を適用して欲しい場合は、事前に病院窓口などで
限度額適用認定証の交付申請の手続きが必要だったのですが、マイナカードがあれば不要になっています。
何かあっても大丈夫なぐらいの貯金をしておくか、もしくは食費やベッド差額分等をフォローできる民間の保険に入っていればよかったかなと思っています。
児童手当 0歳〜3歳未満 15,000円(3年間で540,000円)
妊婦健診助成 同様
乳幼児医療費助成
自治体によります。
マネー調査員の自治体では通称小児医療証ですが、
中3まで対象、自己負担ほぼなし(500円上限)、所得制限なしという条件になりました。
したがって子どもの医療費は、ほぼ掛かっておりません。
出産祝い金(自治体) 90,000円
自治体によります。
第一子ではなかったのですが、時代の流れなのか第二子では市役所から9万円もらえました。
母子手帳を貰いに行くと案内を受けることができました。
母子家庭・父子家庭手当 同様
医療費控除 約40万円
人生で最も医療費を支払ったタイミングでしたので、大いに活用しました。
夫の確定申告で手続きを行い、恐らく40万円ほど返ってきました。
保育料無償化 同様
出産はお金がかかるけど、制度を使いこなせば心強い!
出産でもらえるお金はとても多く制度を併用すれば3年間で600万円以上を貰うことも可能です。
かなり家計を助けてもらいました。
ただし、どの制度も申請が必要だったり、期限があるため、妊娠中からの情報収集と準備がカギとなります!
ちなみに、実感としてはこれだけもらってもすっからかんになります。
3年間で600万円以上と聞こえはいいですが、平均して毎月18万円~19万円ぐらい。
しかもそこから、住民税も払いますし、奨学金の返済も続いてますし、家庭の食費は全額負担だし、自分のスマホ代とか諸々を支払い、子どもの費用も全部が全部、夫が支払ってくれたらいいですが、何かと自分でも購入します。
さらに、保険適用外の出費も多いし(無痛分娩の費用は保険適用外なので15万円ぐらい払いました)
出産ギリギリまで働く予定が、早々に働けなくなりその分給料が入らない、これまで2人で家計を支えていたのに片方の収入が50%までダウンします。
大して服も買わず、髪も半年に一回ぐらいしか切ってないのに、ほとんど手元に残りません。
アメリカでは全然支援がないと聞きましたが、どうやってママたちは生きているのでしょうか。
正直、自分自身にしっかり貯金がある、パートナーにフォローできるだけの稼ぎがある、民間の保険を上手く使う、実家が太い、でないと詰んでおります。
この記事が少しでも役立ったら、シェア・ブックマークしてもらえるとうれしいです。
不明点や気になることがあれば、お気軽にコメントください!
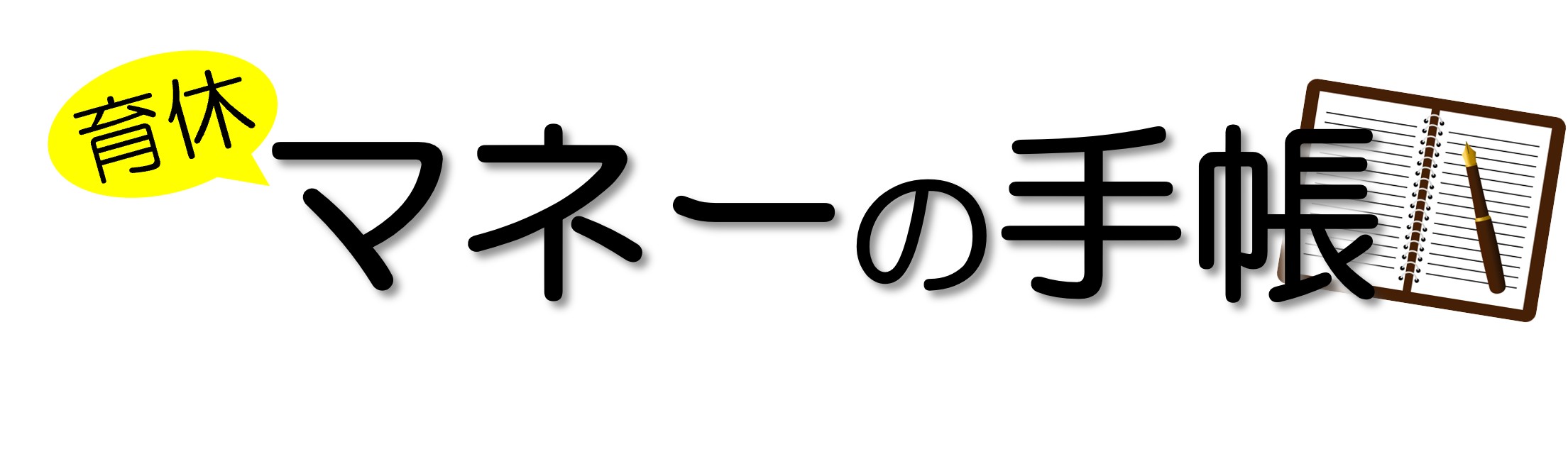





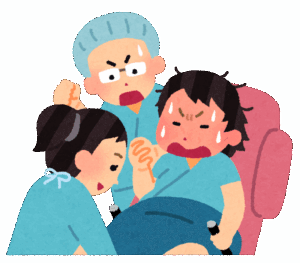

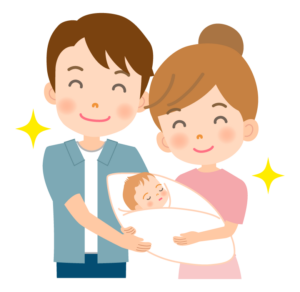
コメント