子どもの預け先も決まり、いよいよ育休明けが近づいてくると、「何を準備すればいいの?」と不安になりますよね。 特に2025年は、育児と仕事の両立を支援する新制度が一気にスタートする注目の年。
2年半の育休を取得して復職したマネー調査員が、「あのときこれを確認しておいて本当によかった」と実感した制度を厳選して7つご紹介します。
特に、2025年から新しく始まる給付金やルールも含めて、最新情報をもとにまとめています!
※この記事の制度はすべて厚生労働省など公的機関の情報をもとに執筆しています
1. 育児時短就業給付金とは?収入減を防ぐ新制度【2025年スタート】
2025年4月から始まった新制度で、給料減額分を補填する給付が受けられます。 これまで「収入が減るのが不安で時短を選びづらい…」という人も、この給付金で選択肢が広がります。この制度は、本人が申請するのではなく会社が申請する必要があります。
マネー調査員も育休復帰後は、色々と考えて時短にしましたが、驚くほど給料が減りましたので、この給付金はとてもありがたかったです!
ただし、支給を受けるには次の受給資格と各月の支給要件を満たす必要がありますので、厚生労働省の資料から一部抜粋します。
資料:育児時短就業給付の内容と支給申請手続(都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク))
- 2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する被保険者であること。
- 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12か月あること。
※過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある場合は、それ以降のものに限ります。育児時短就業開始日前2年の間に、疾病、負傷、出産、育児等やむを得ない理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合は、当該理由により賃金の支払いを受けることができなかった期間を2年に加算することができます(合計で最長4年間)
- 初日から末日まで続けて、被保険者である月
- 1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
- 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
- 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月
支給額のイメージ
育児時短就業給付金の支給額は、原則として次のとおりです。
育児時短就業中の各月に支払われた賃金額 × 10%
ただし、支給額と各月に支払われた賃金額の合計が、育児時短就業開始時の賃金額を超えないように、支給率を調整します。
※1:育児時短就業開始時の賃金月額は、算定した額が470,700円を超える場合は、470,700円となります。また、算定した額が86,070円を下回る場合は、86,070円となります。
※2:育児時短就業給付金には、459,000円の支給限度額がありますので、各月に支払われた賃金の額に支給額を加えた額が459,000円を超える場合は、459,000円から各月に支 払われた賃金の額を減じた額が支給額となります。
※3:また、支給額が2,295円を超えない場合は、育児時短就業給付金は支給されません。
資料:育児時短就業給付の内容と支給申請手続(都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク))
支給申請手続
育児時短就業給付金の支給を受けるためには、被保険者を雇用している事業主の方が育児時短就業開始時賃金の届出、受給資格確認及び支給申請を行う必要があります。
つまり、手続きは会社が行います。条件が色々と複雑なので、復帰後しばらく時短で働く予定の方は会社の担当者に「育児時短就業給付金って受給できますか?」と確認を入れることをオススメします!
資料:育児時短就業給付の内容と支給申請手続(都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク))
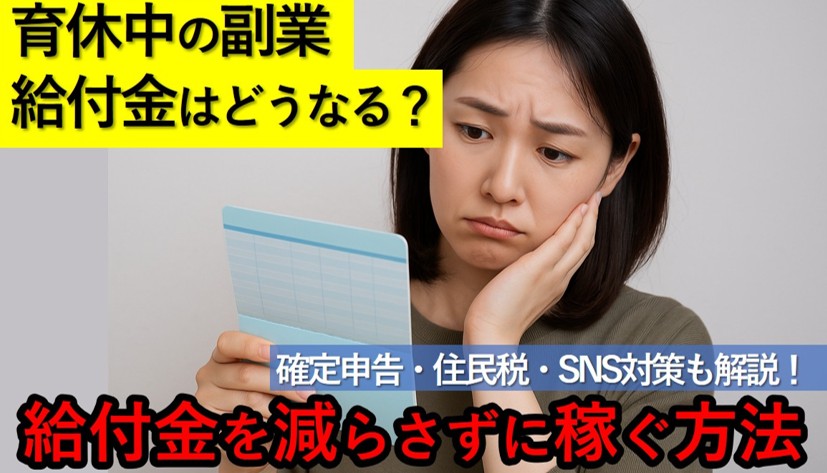
2. 育児・介護休業法の改正ポイント|2025年に変わること
育児介護休業法とは、育児や介護などで時間的な制約を抱えている社員が、家庭と仕事を無理なく両立できるようにすることを目指して制定された法律です。こちらも2025年4月からの制度改正で、以下のような変更があります。
細かい話は色々とありますが、 大まかに言うと、小学校3年生までは子どものために休みが取りやすくなり、小学校に入るまでは残業が免除される。また、3歳未満までは、会社がテレワークできるよう努力してくれるし、仕事と子育ての両立に関して何か個別の事案があれば聞き取りますよ!という内容になっています。
| 項目 | 施行前 | 施行後 |
|---|---|---|
| 子の看護休暇の見直し | 小学校就学の始期に達するまで | 小学校3年生修了まで ①病気・けが ②予防接種・健康診断 ③感染症に伴う学級閉鎖等 ④入園(入学)式、卒園式 |
| 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大 | 3歳未満の子を養育する労働者 | 小学校就学前の子を養育する労働者 |
| 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加 | ①育児休業に関する制度に準ずる措置 ②始業時刻の変更等 | ①育児休業に関する制度に準ずる措置 ②始業時刻の変更等 ③テレワーク |
| 育児のためのテレワーク導入 | 3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化 | |
| 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置 | 令和7(2025)年10月1日から施行 労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。 ① 始業時刻等の変更 ② テレワーク等(10日以上/月) ③ 保育施設の設置運営等 ④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇 (養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年) ⑤ 短時間勤務制度 | |
| 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮 | 令和7(2025)年10月1日から施行 子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間、会社が労働者の意向を個別に 聴取しなければならない。 ① 勤務時間帯(始業および終業の時刻) ② 勤務地(就業の場所) ③ 両立支援制度等の利用期間 ④ 仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等) | |
資料:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和7(2025)年4月1日から段階的に施行(都道府県労働局雇用環境・均等部(室))
3. 時短勤務制度の注意点と対策|復職後の後悔を防ぐには
実は、時短勤務は法律で認められていても、実際の運用には会社ごとの差があります。
- 所定時間:1日5時間か6時間かで負担感がかなり違う
- 申請時期:会社によっては復帰2ヶ月前までの申請が必要な場合も
- 査定・評価への影響:明文化されていないが実態としてある企業も
特に「申請のタイミング」は見落とされがちです。産休に入る前に復職後は時短で、と申し出ていたとしても長い育休でうっかり引き継ぎが出来ていなかったり、ミスが起こっている可能性もなきにしもあらずですので、自分から会社にメールなどで確認してもいいかもしれません。
資料:所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)(厚生労働省)
4. 看護休暇・介護休暇|育休明けの急な対応にも安心
1歳から3歳ぐらいまでは、驚くほど風邪をひき、発熱も日常茶飯事となります。特に復職したては、働きたくて保育園に預けたのに、その保育園から永遠と病気をもらい続けます。でも、これは子どもの成長過程として当たり前ですので有給や看護休暇などの制度を活用して、乗り切るしかありません。
ということで、有給や看護休暇などの制度を改めて確認しておくことをオススメします。
- 看護休暇:法律上は無給だが、企業によっては有給扱いにしている場合も!
- 時間単位での取得が可能か?(勤怠システムの運用も含めて)
- 上司やチーム内での取得文化があるかどうか?
特に、制度はあっても取得しにくい雰囲気などがある場合もあると思います。その場合は、復職前に会社に相談しておくのも手だと思います。そもそも2025年10月以降は、育児・介護休業法の改正に伴い、会社には3歳未満の子どもがいる従業員には、仕事と育児の両立に関する意向を聞き取りする義務があります。まずは、前向きに相談をしてみてください。
5. 病児保育・ファミサポ活用術|預け先問題を解決する方法
実際に使うかどうかは別として、病児保育やファミリーサポートセンター、ベビーシッターの登録は「保険」として絶対に済ませておきたい項目です。何故なら、子どもがいつ体調を崩すのかは直前まで予想が付きません。前日までは元気だったのに、朝起きたら38度以上の発熱、なんてことは珍しくないからです。
そんなときのために、親や家族以外の選択肢があるのは精神的にも安心するものです。しかし多くの場合、どのサービスも急遽当日の対応はNGな場合が多いので、事前の登録をオススメします。
病気中や病気回復期にある子供を、親が仕事などで看れない場合に、一時的に預かり、保育や看護を行うサービスです。どの病院が対応しているかは、自治体のサイトや配布資料、病院ホームページなどで確認できます。
多くの場合、病院に事前に母子手帳や申込書等の書類を提出し、登録手続きを行なう必要があります。
予約方法は自治体によって異なり、病院に直接行なう場合(メール、電話、webなど)もありますし、専用のポータルサイトやアプリで一括管理されている場合もあります。詳しくはお住まいの自治体でご確認ください。
子育ての援助を受けたい人(依頼会員)と、援助を行いたい人(提供会員)を自治体が仲介し、地域で子育てを支え合う仕組みです。保育園の送迎、一時預かり、保護者の急な用事など、幅広いサポートを受けられます。
予約や依頼の方法は自治体によって異なり、電話やメールで直接やり取りする場合もあれば、アプリやポータルサイトでマッチング・依頼ができる場合もあります。詳しくはお住まいの自治体でご確認ください。
多くの場合、まず自治体の窓口やセンターにて、利用希望者が説明会を受け、事前登録を行う必要があります。利用前には、支援を行う提供会員との顔合わせや面談も必要です。
保護者に代わって自宅などで子どものお世話をする有償のサービスです。民間のベビーシッター事業者が提供しており、平日夜間や土日祝、病児対応など、柔軟な依頼ができる場合もあります。
利用するには、事業者の公式サイトなどから会員登録を行い、プロフィールの入力や本人確認を済ませる必要があります。事前にシッターとの面談や見学が可能な事業者もあります。
予約方法は、各事業者のシステム(専用アプリ、web予約など)を通じて行います。対応エリアや料金体系、キャンセルポリシーなども事業者ごとに異なるため、事前によく確認しましょう。
近年、働く家庭の支援として「ベビーシッター利用補助制度」や「割引券(補助券)」を発行する取り組みが、企業・自治体の両方で広がっていますので、利用できそうなものがあるか調べてみてください!

6. 復職面談で制度を活用する方法|伝え方のポイントとは
復職前にある面談(または事前連絡)では、「勤務時間・配属先・働き方」の相談ができる貴重な場です。
さらに、2025年10月以降は、育児・介護休業法の改正に伴い、会社には3歳未満の子どもがいる従業員には、仕事と育児の両立に関する意向を聞き取りする義務もありますので、気になること、不安なこと、確認したいことはぜひ会社に確認しておきましょう。
例えば次のようなことを確認する方もいます。
・「テレワークはできますか?」「通勤時間に配慮できますか?」
・制度を知っていると、交渉材料として活用できる
・言いづらいことこそ、復職前に言うのがベスト
マネー調査員の経験上、どう配慮してほしいのかは具体的に伝えるとよいと考えます。会社としても、プライベートなことですし、家庭によって事情も異なるので、こちらの事情は言わないと想像もつかないことが多々あります。
具体的に、こういうことで困っていて、こうして貰えると助かるんですが相談可能でしょうか?といった具合です。
7. 2025年以降の注目制度まとめ|育休明けに役立つ新制度
近年、少子化社会対策大綱やこども未来戦略方針に基づく施策の一環で、新しい制度が次々と出てきました。
今すぐには関係なさそうでも、今後の育児や働き方に影響する可能性があるため、ニュースには目を通しておくのがオススメです。
- 出生後休業支援給付金(育休直後28日間の手取り100%給付)
- 児童手当の拡充(2024年10月から、高校生まで支給&所得制限撤廃)
- 誰でも通園制度(2025年度一部自治体で開始、2026年度本格化)
資料:2025年4月から「出生後休業支援給付金 」を創設します(都道府県労働局・ハローワーク)
資料:2024年10月分から児童手当が大幅拡充!対象となるかたは必ず申請を(政府広報オンライン)
資料:こども誰でも通園制度について(こども家庭庁)
また、2025年以降に活用が広がりそうな制度として「両立支援等助成金」があります。
企業が子育てや介護との両立を支援するための制度や環境を整備した際に、国から受け取れる助成金のことです。
この助成金にはいくつかのコースがあり、企業がどのような支援を行ったかによって対象が異なります。
たとえば、男性育休を推進する「出生時両立支援コース」や、スムーズな復職を促す「育休復帰支援プランコース」などがあります。どれも会社側の申請が必要ですが、社員側から提案することで制度の導入が進むケースもあります。
資料:2024(令和6)年度 両立支援等助成金のご案内(厚生労働省)
まとめ:制度は知っているだけで“安心材料”になる
2025年は育児支援制度が大きく動く年。復職前のタイミングで、「会社」「自治体」「保育園」それぞれに1回ずつ制度の確認をしておくだけでも、復帰後の不安がぐっと減ります。
何を言えばいいか分からない時は、この記事のチェックリストをそのままメモにして面談や問い合わせに使ってみてください。
育児も仕事も、最初から完璧にはいきません。でも、制度を知っていることが準備になり、安心につながるはずです。
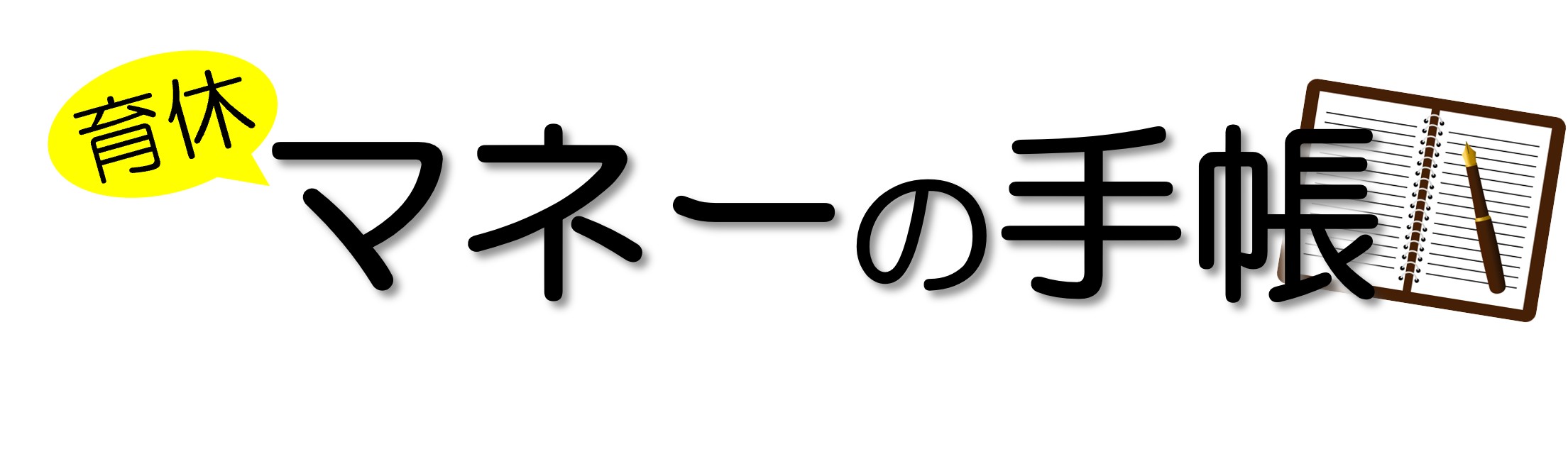
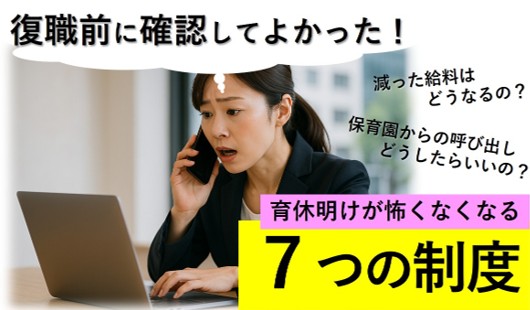








コメント